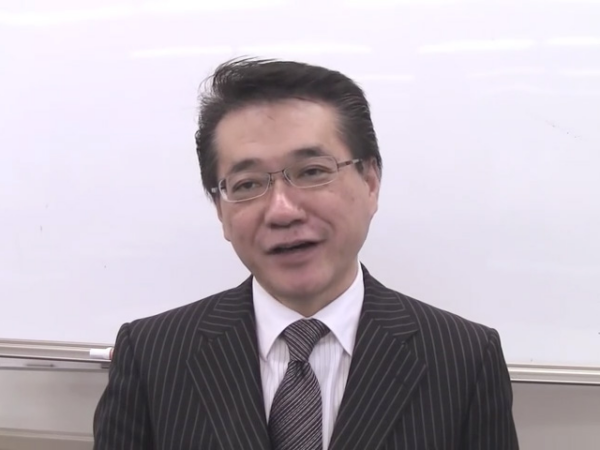「椎名君のコンサルティングって、How toの提供なの?
そんなコンサルタントになるのは、
やめなさい。」
それは、当時の私には刺さるように厳しい言葉だった。
言葉を返す間もなく、目をそらすしかなかった。
だって、How to専門のコンサルタントだったし、
それが貢献することだと勘違いしていたから…
けれど、今にして思えば——
あれは、まぎれもなく覚真だった。
その一言に、私はまだ追いついていなかっただけだ。
あれから22年。
How toの多くが無料で手に入り、
他人の成功事例がSNSで拡散されては消えていく時代になった。
情報は過剰になり、逆に「考えなくても済む仕組み」ばかりが求められている。
だが本当に必要なのは、
「よりその組織らしくあるためには?」という問いを、
組織自身が持ち続ける力だった。
その問いが芽吹いたとき、
コンサルティングは手段ではなく、共に問う場そのものになる。
私たちはただ、
省察を導く媒介者にすぎない。
それ以外に役立てるコンサルティングできることなんてあるのだろうか?
畏れ多いことだと思う。
今はそうありたいと、心から願っている。
数年前のある日、
久しぶりに会ったクライアントに「最近どう?」と声をかけた。
返ってきた言葉は、どこか誠実で、けれど私をざわつかせた。
「仲間と一緒に勉強中です。
誰かが新しい集客の突破口を見つけるのを待っています。
もちろん、私のやり方が仲間たちの突破口になれば嬉しいです。」
その瞬間、私は言葉を失った。
それはやさしい希望のように聞こえたが、
どこかでそれが実現しない夢のように感じたからだ。
たとえ、その突破口が誰かに見つかったとしても、
それは果たして、明日も通じる道なのか?
高度情報化を超えて、
価値のない情報に満ちた時代において、
“誰かの成功”がそのまま模倣されるスピードは、
もはやリスクでしかない。
仮に自社で成功モデルを築けたとしても、
それが「簡単に真似される」ものであれば、
果たしてそれは、本質的な価値と言えるのだろうか?
22年前のあの一言。
それは、コロナ禍によって現実の風景として一気に顕れた。
ノウハウが通用しない世界。
はやりは昨日の価値を陳腐化させ、
「次に当たる何か」ばかりが求められる不安定な戦略。
非本質的なビジネスモデルは、時流に乗っても、やがて沈む。
いや、沈む以前に、誰かの模倣の中に埋もれてしまう。
では、普遍のビジネスモデルとは何か?
それは、「啓眼(けいがん)」の力だ。
たった一つの答えや正解ではなく、
時代を超えて目をひらかせる問い。
つまり、
「私たちは何を成し遂げようとしているのか?」
「顧客は何を求めているのか?」
「強みは何か?」
という問いに立ち戻り続ける力。
その奥から直覚する慧眼。
それは、変化に対して“適応する”のではなく、
通時的に、つまり時間を超えて問い直され続ける感性のことだ。
啓眼とは、まだ見えていなかったものに、自らの目がひらかれていく体験である。
それは他者から与えられるHow toではなく、
自分の内部からじわじわと見え始めていく、根源的な気づきである。
このとき大切なのが、「通時的 vs 共時的」という視点の違いだ。
多くのビジネスは、
「今、何が売れているか?」
「今、誰が成功しているか?」という、
共時的(synchronic)=同時点の比較・競争に依存している。
だが本当に重要なのは、
「この問いはどこから来て、どこへ向かうのか?」という通時的(diachronic)な問い直しだ。
共時的な成功は模倣されやすく、やがて飽和する。
通時的な問いは、深く、長く、自分の組織にとっての意味を含んでいる。
啓眼とは、その通時的な視点に身をおくことでもある。
あの一言を、22年前の私は理解できなかった。
けれどその言葉は、普遍のなりわいとして、今も胸の奥で育ち続けている。